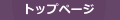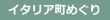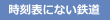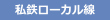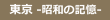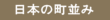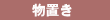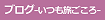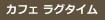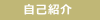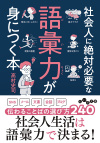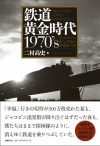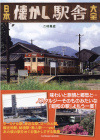2025.06.14 更新

1970年代から90年代はじめにかけて、東京のあちこちを散歩して、おもにモノクロフィルムで町並み、家並みを撮ってきました。 当時は、まだまだ町のそこここに、古きよき「東京」が残っていたような気がします。ここでは、そんな写真を少しずつ公開していこうと思います。
◆のページは小画面対応(Responsive Design/レスポンシブデザイン)です。
| 都区内北東エリア |
| 浅 草 |
| 日光街道 千住宿 |
| 京成関屋・東武牛田駅 |
| 汐 入 |
| 東上野 |
| 墨堤~向島界隈 |
| 押上~業平橋(同潤会中之郷アパート) |
| 京島一丁目 |
| 京島二丁目 |
| 京島三丁目 |
| 都区内南東エリア |
| 総武線 両国~新小岩 |
| 浅草橋 鳥越~馬喰町 |
| 月島~佃島 |
| 芝浦~お台場 |
| 築地~湊 |
| 住吉~千田(同潤会住利共同住宅)◆ |
| 都区内北西エリア |
| 十条台~十条仲原 |
| 中山道 西巣鴨~板橋 |
| 板橋 大門 |
| 赤羽駅西口(旧岩槻街道)◆ |
| 西 台◆ |
| 都区内南西エリア |
| 羽田 弁天橋あたり |
| 旧東海道 品川宿 |
| 代々木上原~駒場 |
●このサイトの古い写真が、おもにモノクロである理由
(カラー写真をわざとモノクロに変換していると誤解する方がいるので)
1. 自分でフィルムの現像・引き伸ばしをしている写真好きにとって、1980年代に入っても、常用するフィルムはモノクロでした。カラーの現像・引き伸ばしは温度管理が非常に難しく、印画紙や薬品の価格も桁違いでした。
2. ネガカラーは発色、粒状性、保存性が悪く、カラーで撮って後世に残し、出版も考えるなら、ポジカラー(スライド用フィルム)しか選択の余地がありませんでした。しかし、ポジは非常に高価である上に、ラチチュード(露出の許容範囲)が狭いという短所がありました。
3. 私のなかでは、ポジカラーは旅行で使うよそいきのフィルムでした。そのうえ、ラチチュードが狭いので町並み写真には向きません。コントラストがつきすぎて、道路の日陰側にある建物は真っ暗になってしまうためです。
4. モノクロフィルムは、量販店で500ft.の長尺フィルムから詰め替えた安価なものが購入できたので、学生の分際でも常用できました。値段を気にせずに気軽にシャッターが押せたので、これだけの記録が残せました。カラーならば、この10分の1も撮れなかったでしょう。
5. 当時の写真集やカメラ雑誌を見ればわかるように、1980年代なかばまで、本格的な写真はモノクロが主流でした。カラー印刷技術が進歩していなかったことに加え、高精細なモノクロフィルムの技術が成熟しており、モノクロの表現力が優れていることが評価されていたためです。
Copyright (c) Takashi FUTAMURA