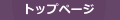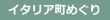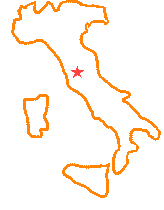
ヴィテルボ(ビテルボ)は、ローマの北数十キロのところにある古い町で、歴史好きや美術好きにはこたえられないところである。
ローマのポーポロ広場そばの駅から私鉄があるというので、行ってみたところ、昼間は直通列車がないとのこと。Saxa Rubra(「サカザ・ルーブラ」と駅員は発音していた)という殺風景な途中駅(現在は改築して立派な駅になったらしい)でバスに乗り換え、1時間半もかかってしまった。
 ▲旧市街の北側に位置するロッカ広場。旧市街で数少ない広い道。
▲旧市街の北側に位置するロッカ広場。旧市街で数少ない広い道。
1996/07
この町には2泊したが、もっとも印象に残っているのは、宮殿でも美術館でもない。旧市街の中心部にある家族経営の小さなトラットリーアなのである。
腹が減ったので夕食をどこかで食べようと、狭い町の中をうろうろと歩いていたのだが、夜の8時にもなろうというのに、どこもガラガラ。ところが、そんななかで、ただ1軒だけ賑わっている小さなトラットリーアがあるではないか。
これは、よほどいい店に違いない。思わぬ発見に舌なめずりをしながら、私はその店に足を踏み入れた。
▼旧市街のプレビシート広場の周囲は、ヴィテルボ最古の地区。 1996/07

 ▲公道をまたいで建物をつなぐ通路が、あちこちに設けられている。 1996/07
▲公道をまたいで建物をつなぐ通路が、あちこちに設けられている。 1996/07
予想に違わず、そこは居心地のいい店であった。60歳ほどの太った主人は、中央のテーブルに陣取り、顔なじみらしい人たちと楽しそうに話をしている。ときに、これまた貫祿のある奥さんが会話に加わる。
一方で、息子と娘は、真剣な顔つきで料理を運びながらも、しばしば父親に怒られている。
もちろん、どんなに忙しくても、勘定は主人の役目である。家族といえど、他人に金を触らせないのは、イタリアの家族経営の店でよく見かける光景だ。
 ▲旧市街の南端にある「Palazzo dei Papi」(パラッツォ・デイ・パーピ)。「教皇たちの宮殿」という意味で、歴代教皇が利用した。
▲旧市街の南端にある「Palazzo dei Papi」(パラッツォ・デイ・パーピ)。「教皇たちの宮殿」という意味で、歴代教皇が利用した。
1996/07
それにしても、これならば店が込むのは当たり前だという雰囲気であった。私自身も、陽気な主人のもとで、実に楽しいひとときを過ごすことができた。
ところがである。その店には、たったひとつ問題があったのだ。
それは、食事がちっともウマくないということである。マズいとまでは言わないが、スパゲッティはアルデンテではないし肉の味付けもいま一つ。これじゃ新宿あたりの安イタリア料理店と変わりない……私は、小さなホテルの小さな部屋で沈思黙考した。
「うーん、たまたま、頼んだメニューがよくなかったのかもしれないぞ。そうじゃなけりゃ、あんなにこんでいるわけがないしなあ。よし、あした、もう一度挑戦してみよう」
翌日は日曜日であった。店は前日以上の混雑ぶりだったが、二晩も続けてやってきた東洋人に対して、主人は握手までして出迎えてくれた。席につくと、私は、なるべく多くの人が食べている品を注文することにした。
▼狭い路地が延々と続く。 1996/07

 ▲宿の窓から見た路地裏の情景。 1996/07
▲宿の窓から見た路地裏の情景。 1996/07
私の席のすぐ前にはテレビが置かれていた。食事を待つ間、ぼんやりと見ていると、ファッションショーがはじまった。場所は、どうやらローマのスペイン階段らしい。
すると、店で一番派手な格好をしていて、私もさきほどから気になっていた若い女性が、私のテーブルにやってきて座るではないか。
もっとも、彼女が、この店の主人の娘の一人であることはわかっていた。それにしても、原宿あたりを徘徊しているコギャルと見まごうばかりの派手なメークに、肩を思い切り出した服。その彼女が、視線をテレビに向けたまま、微動だにしないのである。
「ローマから遠くはないといっても、ヴィテルボは田舎町だよなあ。彼女も、都会にあこがれているんだろう」
 ▲旧市街の静かな通り。
▲旧市街の静かな通り。
1996/07
私は微笑ましく思いながら、目の周囲をべったりと塗りたくった彼女の横顔を見ていたのである。
ところで、問題の食事であるが、やっぱりウマくなかった。でも、雰囲気は満点だった。近所の人びとは、この雰囲気にひかれてやってくるのだろうか。
私は、ワインでぼんやりとした頭のなかで、そんなことを考えながら、安い勘定を払って店を出たのであった。