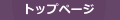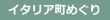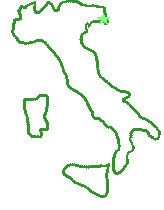
それは1985年の秋のこと。イタリアの東隣に、ユーゴスラヴィア連邦という国があったころの話である。ソ連、ルーマニア、ユーゴスラヴィアを訪ねた私は、いまではクロアチアの首都となっているザグレブから、スロベニアを経由して国境の町トリエステに向かう夜行列車に乗り込んだ。
2等車ではあったが、コンパートメント1室をひとり占めすることができ、トリエステまでぐっすりと睡眠をとれそうだとほくそえんでいたのである。
 ▲中心部にあるカナル・グランデ(大運河)。トップの写真の反対側を見たところ。名前は雄大だが、ヴェネツィアのそれとは違って、海岸から200メートルほど続いているだけ。
▲中心部にあるカナル・グランデ(大運河)。トップの写真の反対側を見たところ。名前は雄大だが、ヴェネツィアのそれとは違って、海岸から200メートルほど続いているだけ。
2008/06
ところが、夜中の2時ごろだっただろうか、どやどやと人の乗り込む気配がしたかと思うと、20歳前後と思われる男女が私のコンパートメントに入ってくるではないか。どうやら、ほかにも同行の友人がかなりいるらしく、しばらくの間、あっちに行ったり、こっちに来たりと騒がしい。
それでも20分ほどすると落ち着いてきたようで、やれやれと思ったのだが、いいかげん目が冴えてしまった。そんな私の様子を見ていたのだろう、男のほうが英語で話しかけてきた。
 ▲トリエステ中央駅。東西冷戦時代には、ユーゴスラヴィアやルーマニアなど、東欧諸国の窓口として賑わった。
▲トリエステ中央駅。東西冷戦時代には、ユーゴスラヴィアやルーマニアなど、東欧諸国の窓口として賑わった。
2008/06
どこから来たのか、なにをしているのかというお決まりのやりとりの後、彼は言った。
「オレたちは、きょうロックのコンサートを聞きに行くのさ」
なるほどと思ったが、こんな真夜中に、しかも手ぶらで国際列車に乗り込んでくるのは不思議だった。そんな疑問を見透かすように説明してくれた。
「トリエステは昔は同じ国だったからね。IDカードさえあればビザなしで行けるんだ」
「へーえ」
「ハードロックは最高さ!」
当時は、東欧の国でもかなり自由化が進み、若者たちにロック熱が高まってきたころだった。そもそも、ソ連とは袂をわかって独自の社会主義路線をとっていたユーゴスラヴィアである。町を歩いていても、ほかの東欧諸国のような重苦しい雰囲気は、ほとんど感じられなかった。
 ▲イタリア統一広場に面して建つトリエステ市役所。
▲イタリア統一広場に面して建つトリエステ市役所。
2008/06
それにしても、80年代なかばといえば、ハードロックがもっとも下火だった時代ではなかろうか。日本では「ハードロックを聴く」などとは、恥ずかしくて口にできなかったころである。真剣な表情で話す彼のことを、私は内心ではにやにやしながら見ていたのだった。
「ところで、日本ではどんな音楽が流行っているんだ」
ここで「ロックさ!」なんて答えたのではおもしろくない。実際に、そのころ日本やヨーロッパでは、ワールドミュージックや民族音楽がちょっとしたブームになっていた。
「うーん、フォークミュージックかな。世界各地のね」
すると彼は、あきれたような顔をしていたかと思うと、それっきり話しかけてこなくなってしまった。
──ちょっと意地悪だったかなあ。でも、本当なんだからしょうがない……。それにしても、不審なやつらである。イタリアの国境で、絶対にしつこく調べられるに違いないぞ。気の毒に……。
 ▲トリエステのオーベルダン広場から出る路面電車。実は、知る人ぞ知る、不思議な乗り物である。詳しくは下の2枚の写真を。
2012/06
▲トリエステのオーベルダン広場から出る路面電車。実は、知る人ぞ知る、不思議な乗り物である。詳しくは下の2枚の写真を。
2012/06
そのあとは、何も話しかけられないのをいいことに、熟睡に入った私であった。目が覚めたのは、国境でイタリアの係員がパスポートチェックにやってきた音がしたときである。
同室のユーゴ人の男女は、IDカードをちょっと見せただけでおしまい。
私は、もちろん日本のパスポートを見せた。すると係員は、「どこを通ってきたんだ」とか「どれがおまえの姓で、どこからが名前なんだ」とか、いやにうるさい。手元のブラックリストらしきものと照合したかと思ったら、次はバッグを開けろという。
1985年のトリエステのトラム


▲路面電車は、ケーブルカー式の車両(オレンジ色)の後押しで急坂を上り、郊外のVilla Opicina(ヴィッラ・オピチーナ)に向かう。現在は、オレンジ色の車両の代わりに、リモートコントロール式の後押し機械が活躍している。 1985/09
久しぶりにイタリア語が聞けたので、うれしくなってべらべらとしゃべったので、かえって変に思われたのか。それとも、こんなルートでイタリアに入国する日本人なんて、めったにいないから不審がられたのか。いずれにしても、バッグの隅々まで見られたなんて、ほかにはソ連に入国したときぐらいである。
──なんだ、なんだ。あいつらのほうが、よっぽど怪しいじゃないか。
そう思ったが、すぐに気がついた。国境の町トリエステでは、いくら社会体制が違うといえども、隣国の青年はなじみが深いのだ。大きなバッグを持って変なイタリア語を話す東洋人のほうが、よっぽど怪しいのである。
 ▲サン・ジュスト城からの町の眺め。
▲サン・ジュスト城からの町の眺め。
1985/09
パスポートチェックも無事に終わると、車窓はもうだいぶ明るくなっていた。列車がトリエステの駅に到着したときには、すでに同室の若者たちは、別のコンパートメントにいる友人のところに行っていたようだった。
私は眠い目をこすって駅を出た。朝だというのに、トリエステの空が、びっしりとうろこ雲におおわれているのが印象的だった。上の写真である。
それから数年後。ユーゴスラヴィア連邦に内戦が勃発する。まっさきに独立を宣言したスロヴェニアでも、次いで独立を宣言したクロアチアでも、連邦軍との激しい内戦があった。
新聞やテレビでそんなニュースを目にするたびに、私はあの夜行列車を思い出すのであった。そして思うのだ。あの「ハードロック」青年もまた、独立のための戦いに加わったのだろうか、無事でいるのだろうかと。